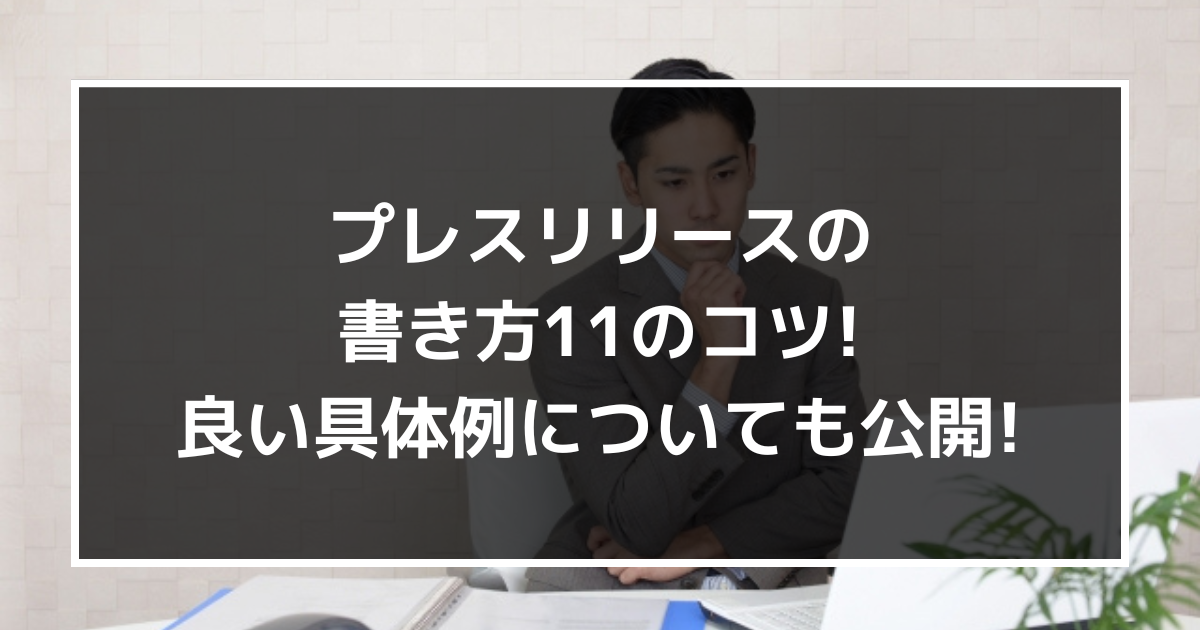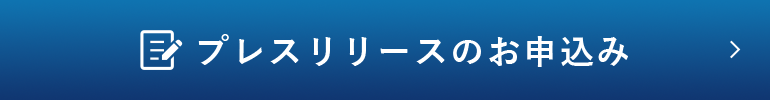自社の取り組みやサービスをもっと多くの人に知ってもらいたいとき、プレスリリースはとても有効な手段です。
実際に書いてみようと思っても「何から書けばいいのか分からない」「この内容で合っているのか不安」と感じる方は多いものです。
とくに医療業界では専門的な情報をどう伝えるかが重要になるため、書き方に悩むこともあるでしょう。
本記事では、そんな方に向けて「プレスリリースの書き方11のコツ」と具体例を交えて解説します。
プレスリリースの書き方に決まりはある?

プレスリリースには法律上の「決まった書き方」はありませんが、読み手であるメディア関係者に伝わりやすくするための“基本の型”は存在します。
とくに医療業界では正確さと信頼性が求められるため、読みやすい構成と適切な情報の伝え方が大切です。
文章構成には基本的な型がある
自由に書いてよいとはいえ、基本となる構成を意識することで、読みやすく伝わるプレスリリースになります。
もっとも一般的な構成は、タイトル→リード文→本文→会社概要→問い合わせ先、という流れです。
とくにタイトルとリード文で「この情報が何なのか」がすぐに伝わるようにすると、メディア側も取り上げやすくなります。
読み手を意識した情報整理が重要
書く側の気持ちばかりを前面に出すと、内容が一方的になってしまいます。
読み手であるメディア担当者や読者が「これは取材する価値がある」と感じられるように、情報を整理することが必要です。
特定の分野に特化したリリースであっても、業界外の人でも理解できるよう意識しましょう。
医療分野は専門性と信頼感がポイント
医療関連の情報は、ときに読者に強い影響を与えるため、内容の信頼性と客観性がとても大切です。
プレスリリースでは誇張を避け、できるだけ事実ベースで情報を整理します。
専門用語は必要に応じて解説を加えたり、注釈をつけたりして丁寧に伝えると安心感につながります。
プレスリリースの書き方11のコツ!

ここではこれからプレスリリースを書こうと考えている方に向けて、基本的かつ実践的な11のコツをご紹介します。
どれも意識するだけで読みやすく、伝わりやすい文章に仕上がるので、ぜひ活用してください。
1. タイトルは「結論」を最初に書く
読み手の興味を引くには、最初の一文が非常に大切です。
タイトルは「どんなニュースなのか」を一目で伝える役割を持ちます。
「新製品を発売しました」ではなく、「〇〇クリニックがAI問診を導入、新規患者対応が3割短縮」など、結果や影響を先に伝えると、訴求力が高まります。
2. リード文で「誰が、何を、なぜ」を簡潔に伝える
冒頭のリード文は、記事の概要を伝える部分です。
「どこの企業が、何を、なぜ始めたのか」を簡潔に記載しましょう。
この部分がしっかりしていると、読み手が本文に自然と入りやすくなります。
3. ニュース性がある内容に絞る
プレスリリースは広報用の「お知らせ」ではありません。
あくまで“ニュースとして扱えるか”が重要です。
「新しい試み」「社会的意義」「独自性」「医療分野への波及効果」など、報道価値のある話題を選びましょう。
4. 難しい言葉は使わず、専門用語には補足を
医療業界では専門用語を避けられない場面もあります。
ただしすべての読者がその用語に精通しているわけではありません。
必要に応じて「かっこ書き」や注釈を添えて丁寧に説明しましょう。
読み手への気配りが信頼につながります。
5. 数字やデータを活用して、説得力を持たせる
実績や効果は、できるだけ具体的な数値で示すようにします。
「患者満足度が向上」ではなく、「患者満足度が前年比20%アップ」と記載すると、内容の信頼性が高まります。
6. 写真や図表があると、理解が深まる
文章だけでは伝わりづらい内容も、画像やグラフを添えることで直感的に理解してもらえます。
たとえば新しい医療機器の写真や、サービスのフロー図などを添付するとより効果的です。
7. 5W1Hを意識した構成にする
「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」は、プレスリリースの基本構成です。
文章が散漫になりそうなときも、5W1Hを整理するだけで伝えたいことがまとまりやすくなります。
8. 第三者のコメントや評価を加える
外部機関の認証や、モニター利用者の感想、医師のコメントなど、第三者の声を加えると、リリース内容に説得力と客観性が生まれます。
とくに医療業界では信頼の裏付けとして効果的です。
9. 自社やクリニックの背景をひとこと添える
どんな思いでそのサービスを始めたのか、企業やクリニックのこれまでの実績などを、短くてもよいので本文中に触れておくと親しみが増します。
企業姿勢を伝えることで、ブランドイメージの向上にもつながります。
10. 問い合わせ先は複数の手段でわかりやすく
リリースの最後には、担当者の連絡先を必ず明記します。
電話とメール、どちらでも問い合わせできるようにしておくと安心です。
営業時間や対応可能な曜日なども添えると、相手が連絡しやすくなります。
11. 文体と形式を統一し、見やすさに配慮する
全体のトーンや文体に統一感を持たせましょう。
また段落の間に空白を入れる、見出しを設けるなどの工夫をすることで、読みやすさが大きく向上します。
メディア担当者が使いやすいように、Word形式またはテキスト形式で送付するのが基本です。
プレスリリースの良い書き方(具体例)を公開!

ここでは実際の構成をイメージしやすいように、プレスリリースの具体例を紹介します。
【タイトル】
福岡市のたなか内科クリニック、AI問診導入で診察前の対応時間を平均32%短縮〜メディカルリンク社の医療DXが現場支援〜
【リード文】
医療機関向けにDX推進を支援する株式会社メディカルリンク(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:田中一郎)は、福岡市東区の「たなか内科クリニック」において、クラウド型AI問診システム『medAI』を導入しました。
本システムの活用により、来院患者への問診・トリアージ業務が平均32%短縮され、診察前業務の効率化とスタッフの業務負担軽減につながっています。
【本文】
■導入の背景
近年、医療現場では人手不足や事務作業の増加が課題となっています。
とくに診察前の問診業務は、医師・看護師ともに時間を要する場面であり、現場の大きな負担の一因となっていました。
■今回の導入内容
たなか内科クリニックでは、2025年3月よりクラウド型AI問診システム『medAI』を導入しました。
患者は診察前にスマートフォンやタブレットから自身の症状や既往歴を選択式で入力することで、受付時にはすでに医師とスタッフに情報が共有されています。
これにより、診察前の口頭問診にかかる平均時間が約6分から4分へと短縮されました(当社調べ、導入前後30日間で比較)。
■成果と評価
導入後1か月で、同クリニックでは以下の効果が見られています。
- 診察前の問診対応が32%短縮
- スタッフの受付業務負荷が約25%軽減
- 問診精度の標準化により、医師による診断精度も安定化
- 高齢患者にも配慮した画面設計で、使用時のトラブルはゼロ
■システムの特徴と今後の展望
『medAI』は、全国50以上のクリニックに導入実績があり、2025年度中には100件以上の契約を見込んでいます。
導入サポートから初期設定、運用支援までワンストップで対応できる体制を整えており、地方の診療所や中小クリニックにも広く活用が進んでいます。
【会社概要とお問い合わせ先を記載】
プレスリリースの書き方に困ったら、一体どうすればいい?

初めてプレスリリースを書こうとすると、どこから手をつけていいのか分からず、手が止まってしまうことがあります。
内容の方向性や表現に迷ったときは、焦らず次のような視点で取り組むのがおすすめです。
第三者目線を取り入れてみる
書いた内容を自分だけで判断せず、社内の他部署や、まったく関係のない友人などに読んでもらうと、思いもよらない改善点が見つかります。
とくに医療分野では、専門的な用語が入りがちなので、一般の人に伝わるかどうかを意識する視点がとても役立ちます。
完璧を求めすぎず「出してみる」ことが大切
プレスリリースは“提出して終わり”ではありません。
必要に応じて後日修正を加えたり、新たなリリースを出したりすることもできます。
最初から完璧な文章を目指すより、「いま出せる情報でしっかり伝える」ことを優先する姿勢が重要です。
外部サポートを活用するのも手段のひとつ
時間がない、広報の専門知識がないという場合は、外部サービスをうまく活用する方法もあります。
医療業界に特化した無料配信サービス「メディカン」では、テンプレートの提供やサポート相談も可能なので、迷ったら気軽に頼ってみるのがよいでしょう。
【まとめ】プレスリリースの書き方に迷ったら、まずはじめに「メディカン」をご活用ください!

今回は「プレスリリースの正しい書き方や11のコツ、良い具体例、書けないときの対処法」について詳しく解説しました。
プレスリリースは内容の伝え方や構成次第で、企業やサービスの印象を大きく左右します。
医療業界では専門性と信頼性が求められるため、丁寧かつ正確な表現が重要です。
無料で配信できる「メディカン」なら、医療業界に特化したサポート体制と、初心者にもやさしいテンプレートをご用意しています。
「どう書けば伝わるのか分からない」といった方は、ぜひお気軽に「メディカン」にご相談ください。
株式会社長利 会社概要
会社名:株式会社長利(英文社名: Nagatoshi, Inc.)
設⽴:2025年5月21日
代表者:上田 恭輔
事業内容:オウンドメディア集客事業、インバウンド事業、PR事業、ホームページ制作事業、インターネット広告事業
URL:https://nagatoshi.jp/